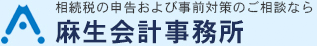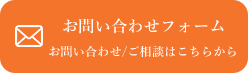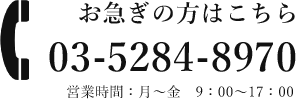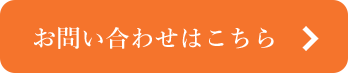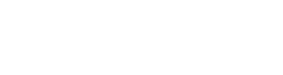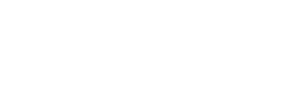お知らせnews
相続税の税務調査は本当に来る?確率と対策を解説2025.07.17
相続税の申告後、「税務調査が来るかも」と不安になる方も少なくありません。調査は、必ず来るわけではありませんが、一定の確率で行われており、申告の内容によっては対象になりやすいケースもあります。
この記事では、調査が来る可能性の目安や、狙われやすいポイント、そして調査を避けるための具体的な対策までをわかりやすく解説します。不安を減らし、準備を整えるための一助としてご活用ください。
相続税の税務調査の確率はどれくらい?
「相続税の申告をしたら、調査が来るかもしれない」と感じる方も多いのではないでしょうか。実際に調査が行われる割合はどの程度なのか、気になるところです。ここでは、国税庁が発表しているデータを基に、調査の確率やその背景をわかりやすく紹介します。
国税局発表の調査割合(実地調査+簡易接触)
国税庁のデータによれば、相続税の申告全体のうち、実地調査が行われる割合は10%程度です。数字にすれば、10人に1人が対象という計算です。やや高い印象を受けるかもしれません。
たとえば、申告内容に不自然な点がある場合や、高額な財産が含まれている場合など、調査の優先度の高まる傾向があります。また、電話や書面での確認といった簡易な接触も含めると、その確率は、さらに17%前後にまで上がるようです。
一方で、残る8割以上の申告については調査対象とならないケースが多いとされています。つまり、誰にでも調査が来るわけではなく、一定の条件が関係していると考えられます。
地域・時期によって確率に差はあるのか?
税務調査の実施には、地域や時期も少なからず影響します。都市部では高額な相続が多いため、調査件数も自然に多くなる傾向があります。逆に、地方では調査対象が分散するため、確率がやや低くなることもあるようです。
また、時期についても一部で傾向がみられます。繁忙期(3月〜5月)を避け、比較的落ち着いた時期に調査が行われやすいと言われています。秋から年末にかけてが、その一例です。
ただし、これらはあくまで一例であり、すべてに当てはまるわけではありません。「調査されるかどうか」は、申告内容や財産構成など、さまざまな要因が複合的に判断されているようです。
税務調査の対象になりやすい申告の特徴とは?

税務調査では、申告内容の中でも、とくに注意を要するポイントがいくつかあります。調査に選ばれる基準は、一様ではありません。ここでは、傾向として調査対象になりやすい申告の特徴を整理してみましょう。
現金・不動産・未上場株が多いケース
相続財産の中に、現金や不動産、未上場株式が多く含まれる場合は、調査対象になりやすい傾向があります。現金は記録が残りづらく、把握しにくい財産の一つ。たとえば、通帳に記載のない現金の出入りがあれば、疑義が生じます。不動産も評価方法に個人差が出やすいため、過少申告のリスクが疑われがちです。
加えて、未上場株式の評価は専門性を要し、適正性の判断が難しいため、税務署の関心が高まるポイントです。
生前贈与の有無・名義財産の扱い
被相続人が亡くなる前に行った贈与が適切に申告されていないと、税務署から指摘を受けることがあります。とくに名義預金や名義不動産といった、形式上は他人の所有でも、実態は被相続人のものである財産には注意が必要です。
こうした財産は「名義財産」として扱われ、相続財産に加算される可能性があります。しかし、明確な贈与契約書があったり、使用履歴が合理的であったりすれば、説明がつく場合もあるでしょう。
申告内容に不明点がある or 税理士を介していない
申告書に整合性の取れない数字や説明不足の項目があると、それだけで調査対象となる可能性が高まります。とくに税理士を介さず、自身で申告書を作成した場合、税務署はその正確性を慎重に確認しようとする傾向があります。
数字の根拠が曖昧であったり、証拠資料が不十分であったりすると、指摘を受けることも少なくありません。いっぽうで、税理士による確認や添付書類が整っていれば、信頼度が増すこともあります。
税務調査が来たら?実際の流れと対応方法
税務署から調査の通知が届くと、不安を感じる方もいるかもしれません。とはいえ、あらかじめ手順を知っておくだけでも、落ち着いて対応できるものです。ここでは、調査の準備から当日の対応、注意すべき点までを順にご紹介します。
実地調査前にやっておくべき準備とは
通知が届いたら、まず調査日と時間を確認しましょう。それから、必要な書類を順にそろえていくことが大切です。たとえば、申告書の控えや財産評価明細、通帳、不動産の登記簿など。これらはすぐに出せるように整理しておきましょう。
一方で、事前に税理士と打ち合わせをしておくと、安心感がぐっと増します。当日の流れを確認したり、想定される質問について助言をもらっておいたりすることで、気持ちに余裕が生まれるはずです。
当日の調査官からの質問と答え方
調査当日は、相続財産の内容や取引の経緯について、調査官から丁寧に質問を受けます。たとえば「この口座の管理者は誰か」「贈与の証拠は残っているか」など。回答に自信がないときは、無理に答えず「確認してお答えします」と伝えましょう。
曖昧な返答や憶測に基づく説明は避けるのが基本です。不正確な発言が後に誤解を招くこともあるため、わからないことはそのままにしておく方が無難です。
追徴資産を避けるためのポイント
調査で申告漏れが見つかると、追加で税金を納めるだけでなく、加算税がかかるケースもあります。これを避けるためには、名義や所有実態が一致しているか、贈与の記録が明確に残っているかを見直しておくと安心です。
しかし、すべてを完璧に管理するのは難しいこともあるでしょう。評価が難しい財産については、早い段階で税理士に相談するのが現実的です。専門家の視点でリスクを事前に減らせることもあります。
税務調査を避けるための対策

税務調査を完全に回避することは、難しいですが、その確率を下げるための対策は存在します。ここでは、調査リスクを軽減するために有効な方法を紹介します。
税理士に依頼するメリットとは?
相続税の申告を税理士に依頼することで、税務調査のリスクを大幅に軽減できます。税理士は税制や評価方法に精通しており、誤りのない申告書を作成してくれます。
また、申告時に添付する「税理士法第33条の2に基づく添付書類」により、税務署が内容を確認済みと判断し、調査対象から外れることも少なくありません。
申告書作成時に気をつけるポイント
申告書を作成する際は、財産の種類や評価方法に応じた正確な記載が求められます。とくに不動産や未上場株式などは評価が難しく、誤解を招く表現は避けることが大切です。
また、控除や非課税枠の適用漏れがないかも注意しましょう。書類の不備があると、それだけで税務署の目に留まりやすくなるため、丁寧な確認作業が必要です。
生前からの対策が有効な理由
相続税対策は、亡くなってからでは間に合いません。たとえば、生前贈与によって財産を分散したり、名義預金の整理をしたりすることで、相続時のトラブルや申告漏れのリスクを抑えることが可能です。
また、被相続人の意向を家族で共有しておくことで、調査時にもスムーズな対応が期待できます。事前準備は安心につながります。
相続税の税務調査に関するよくある質問
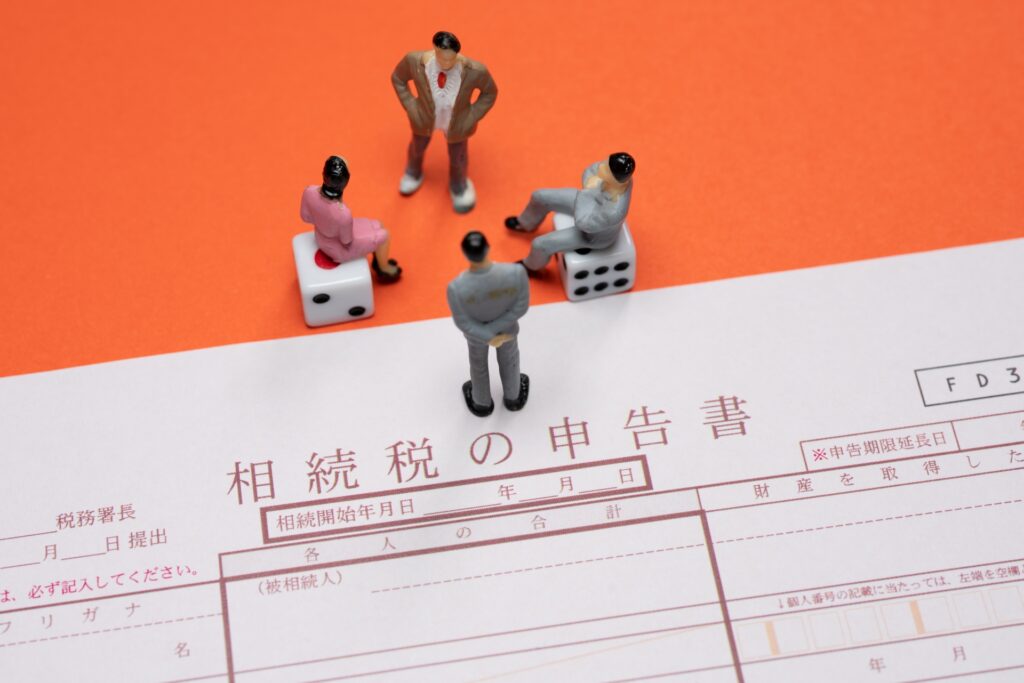
相続税の税務調査については、よく知られていないことや誤解されやすい点も少なくありません。ここでは、お客さまからよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。疑問や不安を解消する手がかりになれば幸いです。
税務調査は誰に来る?全員?
相続税の申告をした全員に、税務調査が行われるわけではありません。国税庁の公表資料によると、実地調査が行われる割合は、全体の約10%。さらに、電話や文書による簡易な確認も含めても2割弱にとどまります。
ただし、申告内容に不自然な点がある場合や、現金・不動産・贈与などの扱いに疑義があると判断されると、調査対象に選ばれる可能性が高まります。つまり、「全員に来る」というより、「条件次第で来る」と理解するのが自然です。
過去の申告でも調査されるの?
はい。税務調査には時効があります。それがすぎるまでの期間であれば過去の申告も対象です。通常、相続税の調査対象期間は5年以内とされています。
しかし、もし申告内容に悪質な隠ぺいや虚偽が疑われる場合には、最大7年までさかのぼって調査されるケースもあります。たとえ何年も前の相続であっても、調査の可能性がゼロとは言い切れません。
調査されたら罰金があるの?
調査の結果、申告漏れが見つかると、追徴課税が発生することもあります。具体的には、足りない税額に対して、「延滞税』「過少申告加算税」、場合によっては「重加算税」が加算されるケースです。
たとえば、計算ミスや書類の不足による軽度な誤りなら10〜15%程度の加算税にとどまりますが、意図的な隠ぺいが疑われると最大40%の重加算税が科されることもあります。いずれにせよ、最初から正確な申告を行うことが、余計なトラブルを防ぐ一番の方法です。
相続税の税務調査とその対策まとめ
この記事では、相続税の税務調査に関する確率や対象となる申告の特徴、調査の流れや避けるための対策についてご紹介しました。調査の対象になるかどうかは、申告の正確さや財産の種類など、さまざまな要因が影響します。
しかし、税務調査は誰にでも起こり得るもの。不安を感じるのは自然なことです。
・事前に税理士へ相談する
・申告書類を丁寧にそろえる
・名義財産や贈与の履歴を整理しておく
このような小さな積み重ねが、大きな安心につながります。
相続税の申告に少しでも不安がある方は、ひとりで悩まずに専門家へ相談することをおすすめします。それが、安心への第一歩になるかもしれません。

麻生 修平
この記事の監修者:
麻生 修平(あそう しゅうへい)
後見業務や終活のサポートなど幅広い相続関連業務に対応
税理士として20年以上のキャリアを生かし、税の申告手続きを中心に、後見人の受任業務や終活のサポートなど、幅広い相続関連業務に応じる。顧客から寄せられる質問や相談事に耳を傾け迅速に対応。
監修者のプロフィールはこちら