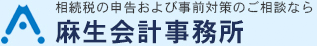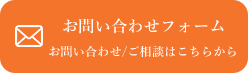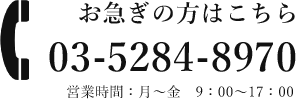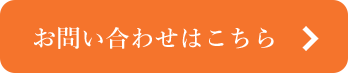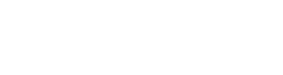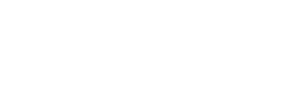お知らせnews
相続税の不動産評価と申告の基本|土地・建物の計算方法と注意点2025.10.02
相続税の申告では、不動産の評価が申告額を大きく左右します。とくに土地や建物の評価方法は複雑で、評価ミスによって余計な税負担が発生することもあるため注意が必要です。
この記事では、不動産評価の種類や具体的な計算方法、そしてよくある注意点について、税理士がやさしく解説していきます。ご自身で申告を検討されている方はもちろん、専門家への依頼を迷われている方にも、判断の参考にしていただければ幸いです。
相続税申告における不動産評価の重要性

相続税の申告において、不動産の評価は課税価格を大きく左右するため、とくに重要です。不動産の評価額は土地や建物の状況によって千差万別であり、専門的な知識が求められます。誤った評価は過大な税負担や申告漏れにつながる可能性があるため、正確な評価が必要です。
以下では、不動産評価がなぜ重要か、どのようなリスクがあるのかを具体的に見ていきましょう。
なぜ不動産評価が申告金額を左右するのか
相続税の課税対象には、現金や預貯金だけでなく、不動産などの資産も含まれます。不動産は、その評価額が大きく、申告額全体に与える影響も大きいため、適切な評価が必要です。
不動産評価を過大にすれば納税額が増え、過小であれば申告漏れと見なされる可能性があります。不動産の評価は、申告内容の正確性と納税額を左右する重要なポイントです。
評価ミスがもたらすリスクとは
不動産の相続税評価で誤りがあると、税務署から申告漏れを指摘され、追徴課税や加算税、延滞税を課される可能性があります。
とくに、評価方法の選択ミスや補正率の見落としによる差異は発見されやすく、税務調査の対象にもなりかねません。評価ミスは単なる計算間違いでは済まされず、ペナルティが発生する重大なリスクとなります。
不動産評価の主な方法と評価対象の種類

相続税の不動産評価では、土地と建物それぞれに異なる評価方法が定められており、評価対象の性質や立地によって適用される方式も異なります。
ここでは、主に用いられる評価手法と、それぞれの対象となる不動産の種類について解説します。正確な評価を行うためには、評価対象をしっかり把握し、適切な手法を選択することが大切です。
土地の評価方法:路線価方式と倍率方式
土地の相続税評価には2つの方式があります。それは「路線価方式」と「倍率方式」です。市街地などでは、国税庁が公表する路線価に基づいて評価する路線価方式が採用されます。一方、路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に所定の倍率をかける倍率方式が用いられます。
地域によってどちらの方式が適用されるかが異なるため、まずは評価対象地の所在地を確認することが重要です。
建物の評価方法と固定資産税評価額
建物の相続税評価は、基本的に市区町村が算定した固定資産税評価額をそのまま用います。建物は土地に比べて評価が安定しており、特例や補正率の適用が少ないため、評価方法としては比較的シンプルです。
ただし、貸家や店舗併用住宅などの場合には、使用状況に応じた補正が必要になることもあります。評価額を正確に把握するためには、最新の課税明細書を確認しておくと安心でしょう。
土地の相続税評価額の計算手順
土地の相続税評価では、評価方法の選定に加え、具体的な計算手順の理解が重要です。ここでは、国税庁が定める路線価や補正率の活用方法、宅地の利用形態による評価の違いについて解説します。
路線価図と補正率の確認方法
路線価方式を用いる場合、まず国税庁の「財産評価基準書」から該当エリアの路線価図を確認します。
路線価は道路に面する土地1平方メートルあたりの価額を示しており、これに土地の面積と各種補正率(奥行価格補正率・側方路線影響加算率など)をかけて評価額を算出します。補正率は土地の形状や接道条件によって異なるため、実務では詳細な読み取りと正確な適用が不可欠です。
宅地の種類による計算の違い(自用地・貸宅地など)
宅地の評価では、その利用実態に応じて評価方法が異なります。自宅や別荘など自ら利用している土地(自用地)は、そのままの評価額を用います。
一方、他人に貸している土地(貸宅地)は、借地権割合を考慮して評価額が減額されるのです。そのため、相続税額も低くなる傾向があります。利用形態の判定を誤ると評価額に大きな違いが生じるため、現状の使用実態を正しく把握することが重要です。
建物の相続税評価額の計算手順
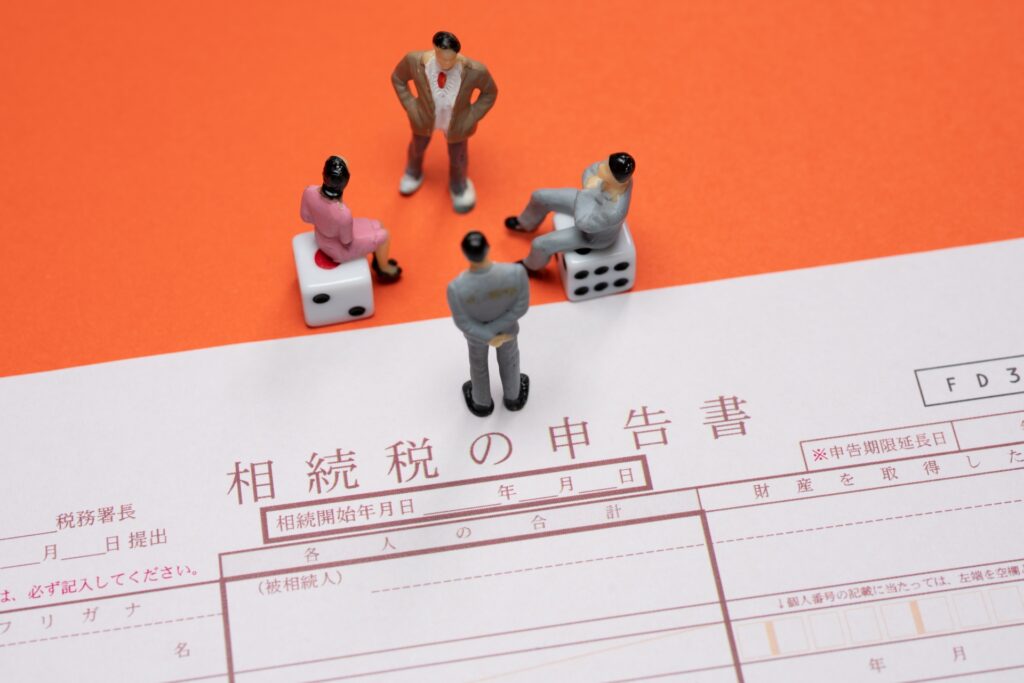
建物の評価は、土地と異なり比較的単純です。しかし、使用状況や権利関係によって評価額が変動する場合もあります。以下では、固定資産税評価額に基づく基本的な算出方法と、賃貸物件やマンションなど特殊なケースでの評価の考え方を解説します。
固定資産税評価額から算出する方法
建物の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額をそのまま使用します。これは、市区町村が評価し課税明細書に記載される額であり、建物の構造や築年数、用途に基づいて決定されています。
評価額を確認するには、最新の固定資産税納税通知書や課税明細書を入手するのが確実でしょう。複数棟を保有している場合や評価に不安があるときは、専門家の助言を受けるとよいでしょう。
貸家・区分所有建物の評価の考え方
賃貸中の建物は、利用制限があるため評価額を下げる仕組みになっています。これを「貸家評価」と呼び、固定資産税評価額に借家権割合(通常30%)をかけて減額します。
また、マンションなどの区分所有建物の場合は、共用部分の割合や専有面積に応じた敷地権の評価も必要です。賃貸状況や権利関係を正確に把握することが、正しい評価につながります。
相続税評価における特例と減額要素
相続税の不動産評価には、一定の条件を満たすことで評価額を軽減できる特例や制度が用意されています。これらを適切に活用することで、納税額を大きく抑えられる可能性があるのです。
ここでは代表的な特例である「小規模宅地等の特例」や、土地の形状や立地条件に基づく評価減の考え方を解説します。
特例の要件や適用の判断は専門的な確認が必要なため、実際の申告では専門家のサポートを受けることが有効です。
小規模宅地等の特例とは
相続税には、特定の要件を満たした宅地に対して評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」が設けられています。たとえば、自宅の土地を相続した場合には、最大80%の評価減を適用されることがあります。
この特例を適用するには、相続人の居住状況や申告期限内の手続きなど、厳格な条件を満たすことが必要です。制度を正しく理解し、事前に準備することが節税につながります。
利用価値の低下した土地の評価減
傾斜地や不整形地など、一般的な土地に比べて利用価値が著しく劣る場合、相続税評価額を一定程度減額できることがあります。これは「利用価値が著しく低下している宅地」として、補正率を用いて評価額を引き下げる制度です。
具体的には、間口が狭い、奥行が極端に長いといった形状上の問題が該当します。現地の状況を正確に把握し、適用可能かどうかを専門家に確認することをおすすめします。
不動産評価ミスによる申告リスクと注意点
不動産評価を誤ると、追徴課税や税務調査のリスクが高まります。ここでは、評価ミスによるペナルティや修正手続きについて解説します。
誤った評価が招く追徴課税
不動産評価を誤って過少に申告した場合、税務署からの指摘を受けて追徴課税される可能性があります。過少申告加算税や延滞税が課され、結果的に本来の納税額よりも多く支払うことになるケースもあります。
とくに、意図的でなくとも評価方法の誤解や確認不足によるミスが多いため、慎重な確認と専門的な知識が必要です。
修正申告・加算税の対応
評価ミスに気づいた場合は、速やかに修正申告することが重要です。自発的に修正申告すれば、加算税が軽減または免除される可能性もあります。しかし、税務調査を受けてから申告した場合は、重加算税が課されることもあります。
適切な対応のタイミングと手順を理解し、状況に応じた判断をするには、税理士など専門家の助言を仰ぐのが得策です。
不動産評価のミスは、申告全体の信頼性を損なう大きなリスクとなります。こうしたリスクを回避するためにも、正確な評価と適切な申告が不可欠です。より詳しい内容は、以下のページで解説しています。
相続税申告の不動産評価は専門家に依頼すべき?
不動産の相続税評価は、評価基準の複雑さや申告の精度が求められるため、多くの人が悩むポイントです。
ここでは、評価ミスがもたらすリスクや、専門家に依頼することで得られるメリットをご紹介します。また、麻生会計事務所のサポート体制についてもご案内し、依頼を検討する際の参考となる情報をお伝えします。
不動産評価ミスは相続税申告のリスクに直結する
相続税の申告において、不動産評価の誤りは申告全体の信頼性に影響を与えます。とくに土地の形状や接道条件によって補正率が異なるため、評価に関する専門知識が不可欠です。
誤った評価をもとに申告すると、税務調査の対象となり、結果的に追徴課税が発生するリスクもあります。不動産は資産の中でも金額が大きく、評価ミスの影響も重大です。
相続税申告をスムーズに進めるにはスピードと経験がカギ
相続税の申告には期限があり、遺産分割協議や各種書類の準備も含めて時間との勝負です。経験豊富な専門家に依頼すれば、必要な手続きを的確に案内してくれるため、無駄な手戻りを防げます。
また、特例や減額制度を正しく適用することで、節税の可能性も広がります。迅速かつ正確な申告を行うためには、税理士のノウハウが大きな力となるのです。
代表税理士が直接対応する安心感と“共創”の姿勢
麻生会計事務所では、代表税理士が初回相談から申告完了まで一貫して対応します。事務的なやり取りに終始せず、依頼者とともに考え、寄り添いながら最適な申告を作り上げていく“共創”の姿勢が特徴です。
不安や疑問をその場で相談できる体制は、初めて相続を経験する方にとって大きな安心材料となるでしょう。
相続税の申告をスムーズかつ確実に進めるためには、税理士への依頼を検討するのが有効です。費用や依頼の流れなど、気になる点については下記のページで詳しく解説しています。
※内部リンク:「相続税申告は税理士に依頼すべき?費用・選び方・手続きまで解説」
正しい不動産評価で相続税の無駄を防ぐ|申告前に確認したいポイント
不動産の評価は、相続税の計算において非常に大きな影響を持ちます。ここでは、正確な評価がなぜ節税につながるのか。また、専門家のサポートを受けるべきタイミングについて、実践的な観点から解説します。
正確な評価が節税につながる
相続税においては、不動産の評価がそのまま課税対象額に反映されるため、正確な評価が節税の第一歩になります。評価を正しく行えば、不要な税負担を回避でき、特例や控除を適切に活用する余地も広がります。
過大評価により本来払わなくてもよい税金を支払ってしまうケースもあるため、事前に評価方法を理解し、必要であれば専門家のチェックを受けることが重要です。
無理せず専門家に相談することも大切
不動産の評価や相続税申告は、法律や通達に基づく専門的な判断を求められる場面が多く、無理に自分だけで対応しようとすると、かえってミスや時間のロスにつながることがあります。
とくに評価額が高額又は土地が広大な場合や、複数の土地・建物がある場合は、専門家に早めに相談することで、手続きの簡略化と正確性が両立可能です。信頼できる税理士と連携しながら進めることが、円滑な相続のポイントとなります。