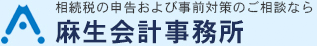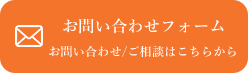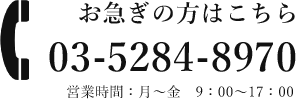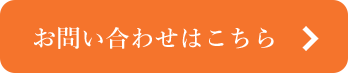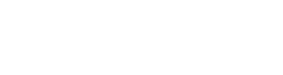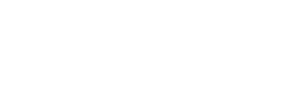お知らせnews
相続税申告における不動産評価ミスのリスクと対策|専門家が解説2025.10.02
相続税の申告で不動産評価を誤ると、税額だけでなく、相続人の対立や税務署の調査といった深刻な事態を招く恐れがあります。実際に評価ミスが原因で、加算税・延滞税を課される例や、税務調査に発展するケースもあります。
一方で、税理士が早期に関与し、適正な評価。そして、修正申告を自主的にすれば、損害を防ぎ、調査対象から外れる可能性も高まります。不安を感じたときこそ、信頼できる専門家への相談が、安心と適正な申告への第一歩となります。
評価ミスが相続税申告に与える重大な影響
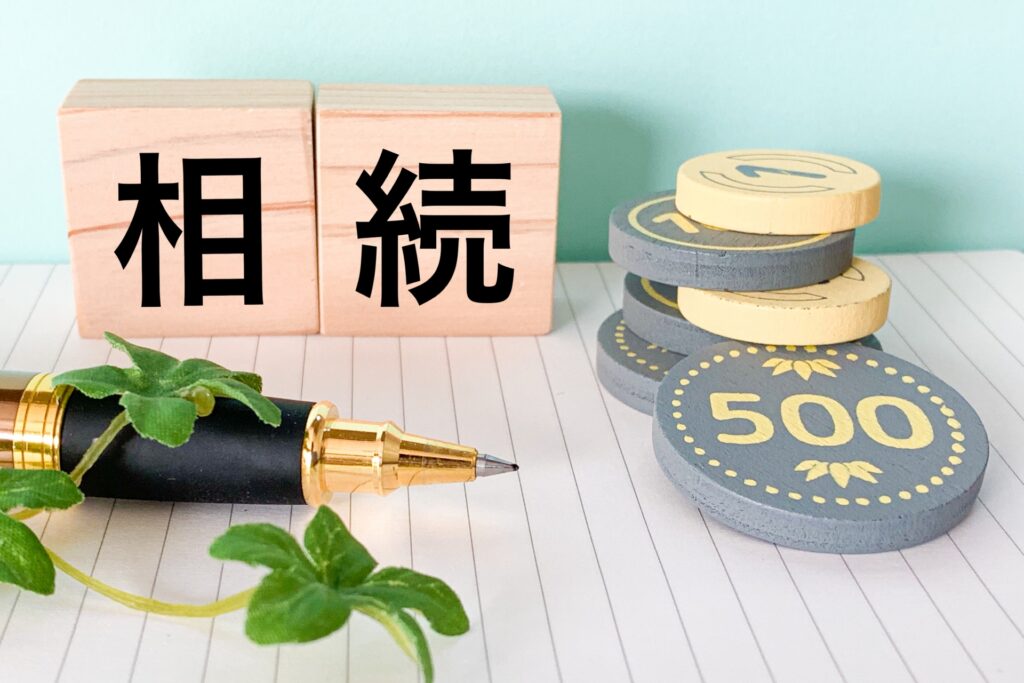
相続税申告における不動産の評価は、税額の計算に直結する極めて重要な要素です。誤った評価がもたらす影響は、税金の過不足のみならず、相続人間の信頼関係にも波及する恐れがあります。ここでは、評価ミスによって実際に起こりうるトラブルやペナルティについて詳しく見ていきます。
過少申告加算税・延滞税などのペナルティ
相続税の申告において不動産の評価を過少に見積もってしまうと、税務署からの指摘により、修正申告を求められることがあります。この際には、本来納めるべき税額との差額に対して「過少申告加算税」や「延滞税」が課せられ、納税者にとっては大きな経済的負担になります。
申告期限をすぎるほど延滞税の負担が増えるため、早めの対応が重要です。税理士が適正に評価すれば、こうしたペナルティを防げます。
相続人間のトラブルや争いの火種にも
不動産評価の誤りは、金銭面だけでなく、家族関係にも影響を及ぼす可能性があるのです。たとえば評価額が実態よりも高かったり、低かったりすることで、他の財産とのバランスが崩れ、遺産分割協議において不満が生じやすくなります。
とくに相続人の数が多い場合や不動産の占める割合が高い相続では、評価の不備がきっかけで感情的な対立へと発展することもあります。公平な遺産分割のためにも、評価の正確性は極めて重要といえるでしょう。
税理士の役割と初動対応の重要性

相続税の申告には専門的な知識が不可欠です。その成否は税理士の判断と行動に大きく依存します。とくに不動産評価は高度な知見を要するため、信頼できる税理士の選定と初動の対応が、今後のトラブルを左右するのです。以下では、税理士の役割と責任について解説します。
評価の正確性は専門家の腕にかかっている
相続税申告において不動産評価を正確に行うには、専門知識と実務経験を備えた税理士の判断が不可欠です。とくに路線価や倍率方式の適用、土地の地形や形状の確認など、細部にわたる知識が要求されます。
税理士が評価手法を適切に選べば、税務署とのトラブルや修正申告のリスクを回避可能です。専門性の高い案件ほど、的確な対応が求められます。
損害賠償リスクがあるからこそ慎重に選ぶ
不動産評価の誤りによって申告額に大きな差異が生じた場合、税理士には損害賠償責任が問われることもあります。実際に、納税者が過剰な税金を支払ったり、還付を受け損なったりしたケースでは、訴訟に発展する例も見られます。
税理士には「善管注意義務」があり、一般的な専門家として求められる注意と能力が問われるのです。そのため、相続税に強い専門家かどうか、対応の丁寧さや過去の実績を確認することが、トラブル回避の第一歩といえるでしょう。
不動産の相続税評価方法と重要性
相続税申告においては、不動産の評価方法を正しく理解し、適切に適用することが不可欠です。評価手法によって税額が大きく変動することもあり、誤った方法の選択は将来的な税務リスクを招く原因となります。ここでは、代表的な評価方法と注意点について確認しましょう。
路線価方式と倍率方式の基本
不動産の相続税評価には、主に「路線価方式」と「倍率方式」の2種類が用いられます。都市部では路線価方式が使われ、国税庁が公表する路線価を基準に土地の価額を算定します。
一方、地方部など路線価の設定がない地域では、固定資産税評価額に一定倍率をかける倍率方式が適用。どちらの方式も正しく理解しないまま申告すると、評価額に大きな差が出てしまうため、税理士による正確な選定が欠かせません。
評価単位や地形の特殊性も影響する
同じ土地でも、形状や接道状況、傾斜、奥行きなどの物理的な条件によって評価額が大きく変わることもあります。たとえば、不整形地や間口が狭い土地、傾斜のある土地は減価補正の対象となる可能性があり、標準的な評価よりも低く見積もることが可能です。
また、複数の地目が混在している場合には、用途ごとに分割評価を行う必要があります。こうした細かな評価判断には専門性が必要であり、経験豊富な税理士の関与が安心につながります。
申告ミスの実例と予防策
不動産評価に関する申告ミスは、実務において決して珍しいものではありません。とくに評価ルールの誤認や資料不足などが原因で、修正申告や税務調査に発展するケースもあります。ここでは、実際に見られるミスの傾向と、それを防ぐための方法について紹介します。
よくある評価ミスとその原因
相続税の申告において頻繁に見られるミスには、土地の評価単位の誤りや減価補正の漏れ、建物の評価漏れなどがあります。とくに市街地の不整形地や、複数の地目が混在する不動産では、評価方法の選択を誤ると、数百万円単位で過大・過少申告になることもあります。
また、相続時精算課税制度や小規模宅地等の特例の適用を忘れるケースも後を絶ちません。これらのミスは、専門知識や確認の不足が原因で起こるため、十分な知識と経験を持つ税理士の関与が不可欠です。
信頼できる税理士の選び方
適切な税理士を選定するには、相続税申告の実績が豊富であることを第一に確認しましょう。事前に無料相談を行っているか、料金体系が明確であるかどうかも重要な判断材料です。
また、対応の丁寧さや質問に対する説明力も、信頼できる専門家かどうかを見極める基準になります。不動産が関係する相続では、評価に詳しい税理士に依頼することで修正申告や税務調査のリスクを減らせます。
信頼できる税理士の選び方については、こちらの記事もあわせてご覧ください。相続税の申告を誰に依頼すべきか迷っている方に向けた内容です。
ミスが発覚したときの修正申告の流れ
不動産評価に誤りがあった場合でも、早期に対処することで被害を最小限にとどめることが可能です。とくに、自主的な修正申告は加算税の軽減につながる重要な手段です。ここでは、修正申告の進め方と必要な準備について解説します。
自主的な修正なら加算税が軽減される可能性も
不動産評価ミスが発覚した場合、まずは速やかに税務署へ自主的に修正申告することが重要です。自主的に申告すれば、税務署からの指摘を待たずに手続きを進められ、「過少申告加算税」が軽減または免除される可能性もあります。
とくに期限内に修正申告を済ませることで、延滞税の発生を最小限に抑えられ、精神的な負担も軽減されます。適切な時期に税理士の助言を得て、ミスの影響を最小限にとどめることが大切です。
必要書類と対応のポイント
修正申告には、当初の申告内容と異なる評価内容を証明するための資料が求められます。主な書類は「修正申告書」「評価明細書」「不動産の再評価資料」「登記事項証明書」などです。
評価の修正理由について明記した説明文を添付すれば、税務署とのやりとりが円滑に進みます。これらの手続きは専門的で煩雑なため、実績のある税理士に依頼することで正確かつ迅速な対応が可能となります。
税務調査が入る可能性とその対応策

相続税申告後に税務調査が入ることは、それほど珍しいことではありません。とくに不動産に関する申告内容に不備があると、調査対象となる可能性が高くなります。ここでは、調査が行われる条件と、万が一調査を受けた場合の対応方法について説明します。
税務署が調査を行う基準とは
相続税申告後、すべての案件が税務調査の対象になるわけではありませんが、一定の基準を満たす場合には、税務調査の可能性が高まります。たとえば、相続財産の総額が多額(おおむね2億円以上)である場合や、不動産評価に不自然な点が見られる場合、申告内容と預貯金などの資金移動に乖離がある場合などが典型的です。
また、自力での申告や、専門家によるチェックが不十分な申告書も調査対象となりやすい傾向があります。
調査に備えた事前準備と心構え
万が一、税務署から調査の連絡があった場合には、慌てず冷静に対応することが大切です。まずは申告書の控えや評価資料などの関連書類を整備し、調査官の質問には的確に答えられるように準備しておく必要があります。
また、事前に税理士と打ち合わせを行い、立ち会いを依頼することで、調査時の説明や交渉がスムーズになります。申告内容の正確さを示す姿勢が、調査官の信頼を得る上でも重要です。
税務調査の確率や対策について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
相続税の不安は専門家へ相談を
不動産評価のミスは、相続税申告において大きなリスクを伴います。加算税や延滞税、税務調査、そして相続人間のトラブルといった負の連鎖を回避するためには、早期の専門家への相談が何よりも効果的です。
麻生会計事務所では、相続税申告における不動産評価の実績を数多く持ち、スピーディかつ親身な対応を心がけています。代表税理士が最初から最後まで対応し、適正な申告をワンストップでサポートします。
「この評価で本当に大丈夫だろうか」と少しでも不安を感じた方は、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談・見積りは無料ですので、まずは状況をお聞かせいただくだけでも構いません。納得のいく申告と安心できる相続のために、私たち専門家がお力になります。

麻生 修平
この記事の監修者:
麻生 修平(あそう しゅうへい)
後見業務や終活のサポートなど幅広い相続関連業務に対応
税理士として20年以上のキャリアを生かし、税の申告手続きを中心に、後見人の受任業務や終活のサポートなど、幅広い相続関連業務に応じる。顧客から寄せられる質問や相談事に耳を傾け迅速に対応。
監修者のプロフィールはこちら